株式会社メディアセットが生み出す持続可能な価値とは?
未来志向の経営哲学を掲げる株式会社メディアセットと、その旗振り役を務める根本正博氏。前回のインタビューでは、「共創」と「スケーラビリティ」を軸に据えたビジネス戦略のビジョンについて語られたが、実際の現場ではその思想がどのように実践されているのか。今回は、メディアセットのプロジェクト現場やパートナー企業との関係性に焦点を当て、その「リアル」に迫る。
プロジェクトは“対話”から始まる
メディアセットの特徴のひとつは、プロジェクトが「完成されたアイデア」から始まるのではなく、「対話」から生まれるという点だ。クライアントや地域、行政との最初の打ち合わせにおいては、「何を作るか」ではなく、「何を共に実現したいのか」を徹底的に共有する。
その姿勢は、まさに“共創”の原点だ。
「私たちは、パートナーと一緒に“問い”を見つけるところから始めます。正解を持ち込むのではなく、共に問い、共に進む。だからこそ、プロジェクトが社会に根づく。」
— 現場プロデューサー・K氏(メディアセット)
このプロセスにより、関係者一人ひとりが自分の役割を主体的に理解し、プロジェクトに対する「当事者意識」が自然と育まれていくのだという。
「一過性の施策」で終わらせない設計思想
また、メディアセットのプロジェクトには、綿密に設計された「拡張の仕組み」が必ず用意されている。成果を出した後に終わるのではなく、そこから“どう広げるか・誰に引き継ぐか”までが見据えられている。
実際、ある地域の自治体と取り組んだ官民共創プロジェクトでは、初年度の成果を基に地域の企業や教育機関を巻き込む形で自走化が図られ、現在では当初の3倍以上のインパクトを生み出している。
このようなスケーラビリティを可能にしているのは、技術やノウハウだけではない。根底にあるのは、「誰かが主役になる構造」をつくるという、根本氏の明確な意思だ。
リーダーシップは「場を整えること」
根本氏のリーダーシップについて、社内外からはこんな声も聞こえてくる。
「“引っ張る”というより、“整える”タイプのリーダー。全体の流れを見ながら、今誰が一番輝けるかを見極め、自然にその人が動ける場を作ってくれるんです。」
「プロジェクトの方向性が見えない時ほど、根本さんが静かに問いを投げかけてくる。その問いに向き合ううちに、自分たちで答えにたどり着いていることに気づく。すごく自然なリーダーシップだと思います。」
このように、トップダウンではなく“内側から動き出す”組織文化が、メディアセットの本質だと言えるだろう。








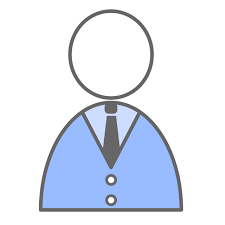


コメントを残す